
女性「メラトニンってなんですか?これが増えれば眠れるようになりますか?」
こういった疑問にお答えします。
この記事を書いている私は,現役パーソナルトレーナーで,医療機関でリハビリテーションとしても働いています。栄養やトレーニング論を専門とします。
メラトニンとは,眠りを促してくれるホルモンのひとつです。他にも,強い抗酸化作用やダイエット効果も見込めるホルモンです。
今回はメラトニンについて説明します。
本記事の内容
・メラトニンとは
・メラトニンの効果
・分泌が多い時間帯
・ダイエット効果はあるのか
・セロトニンとの関係
・寝つきを良くするには
メラトニンとは

-
メラトニン(melatonin)
人や動物に存在するホルモン
概日リズム(サーカディアンリズム)の調整作用をもつ
ホルモンのひとつで,主に人の睡眠を調整してくれるホルモンです。このホルモンのおかげで,人は眠気がきて眠くなったりと,夜にしっかりと眠れる準備をしてくれます。
反対にメラトニンが少なくなると,眠気がこず,良質な睡眠ができないため,注意が必要です。
メラトニンの効果

②概日リズムの調整
③抗酸化作用
④ダイエット効果
⑤性腺抑制作用
①催眠効果
一番の効果は催眠効果でしょう。
そのため「睡眠ホルモン」とも呼ばれます。
メラトニンは脈拍・血圧・体温を低下させ,体を睡眠へと誘う効果があります。寝つきが良いことで良質な睡眠へと繋がるため,メラトニンの分泌は欠かせません。
日本では販売していませんが,海外ではメラトニンのサプリメントを購入できるドラッグストアがあるくらい,一般的なものです。
②概日リズムの調整
メラトニンは朝に分泌が少なく,夜に増加する傾向があります。そのため,概日リズムとして,1日の流れを整えてくれます。
夜更かし,昼夜逆転などは概日リズムを乱すことにも繋がり,避けたい点です。
メラトニン分泌の詳細については,後述します。
③抗酸化作用
メラトニンには強い抗酸化作用があります。
活性酸素が除去されるため,老化の防止やアンチエイジングの効果が期待できます。
また,抗酸化作用で免疫力も高めることができ,しっかりと分泌を促進させてあげたいです。
④ダイエット効果
夜眠っているときには,様々なホルモンが分泌されています。眠りがしっかりと取れない場合は,ホルモンが分泌されず,代謝を低下される原因にもなります。
ダイエット効果も次章以降を参照してください。
⑤性腺抑制作用
日本でサプリメントを販売していない理由もこのためです。眠気がこないから,安易にメラトニンを過剰摂取すると,性腺が抑制されていまします。
性腺刺激刺激ホルモン
・黄体化ホルモン
・卵胞刺激ホルモン
この2つのホルモンが抑制されると,卵胞や精子の成長にも関与し,成長・発達に悪影響があります。そのため,生殖機能の低下が起きます。
もしサプリメントを購入して摂取する場合には,摂取量をかならず守りましょう。
分泌が多い時間帯
メラトニンは脳の松果体から生成されます。
・朝:一番分泌量が低い
・夜:一番分泌量が高い
早朝が一番低く,血中のメラトニン濃度は1pq/ml程度。その後,15時間ほど経過し徐々に上昇,メラトニン濃度が60〜70pg/mlになると眠気がきます。
メラトニン濃度のピークはAM:3時頃で徐々に低下します。
メラトニンは年齢によって低下する?
寝る子はよく育ちますよね。それを裏付けるように子ども,とくに赤ちゃんはよく寝ます。
赤子ではメラトニンの分泌は最大で,加齢によって徐々に低下することがわかっています。とくに高齢になって寝つきが悪いのは,このためです。
寝つきが悪いほど睡眠の質は低下し,疲れが溜まって次の日の仕事に影響を及ぼします。
もし,寝つきが悪く疲れが取れない場合は,サプリメントで寝つきを改善することも必要です。
ダイエット効果はあるのか

睡眠中には様々なホルモンが分泌されます。
・コルチゾール
・メラトニン
・レプチン,グレリン
睡眠中に大事なのは,成長ホルモン。
成長ホルモンが分泌されることで,疲労を回復したり,新陳代謝を促しています。
とくに最初の3時間に成長ホルモンが分泌されるため,睡眠の「長さ」「深さ」は重要になります。
睡眠が浅かったり,不足すると成長ホルモンの分泌も抑制され,代謝も落ちてしまいます。
事実,睡眠不足により肥満になるリスクが高まる報告がいくつも発表されています。
睡眠と肥満は関係性が立証されているため,しっかりと睡眠をとることをおすすめします。
セロトニンとの関係
メラトニンは催眠作用がありますが,セロトニンと深く関係があります。
メラトニンはセロトニンを材料にして作られるため,セロトニンは重要です。そして,セロトニンは必須アミノ酸のトリプトファンから生成されます。
アミノ酸スコアの高い食品をしっかりと取れているでしょうか。寝つきが悪い場合は,食事を見直す必要もあります。
催眠を促したい場合は,まずアミノ酸を摂取することもおすすめです。
寝つきを良くするには
・適度な疲労感 ・栄養のとれた食事 ・就寝1時間前の入浴
まずは,この3点を気をつけましょう。
適度な疲労感
人は疲れると体を休めようとします。
その働きを利用して,軽い運動を習慣化しましょう。すると,夜には自然と眠くなります。
軽い運動をすることで,快眠効果が期待できることは実証されています。
反対に激しい運動は眠りを妨げるため,もし運動をするのなら軽めの運動にしておきましょう。
栄養のとれた食事
さきほど話した通り,栄養のとれた食事は睡眠を促します。
トリプトファンはアミノ酸で,アミノ酸スコアが高い食材に含まれています。タンパク質の豊富な肉類・魚類を多く摂取しましょう。
就寝1時間前の入浴
入浴は副交感神経を優位にし,心も体もリラックスさせます。すると,体は眠りに向けて準備を始めます。
入浴で暖まった体は徐々に適温へと戻っていきます。体温が落ち始めると共に眠気も始めるため,睡眠を促したいときは入浴が大切です。
NG行動
メラトニンの分泌は規則正しい習慣によって分泌されます。
しかし,不規則な生活はメラトニンの分泌させることがわかっています。そのため,下記の項目には気をつけましょう。
・就寝前のスマホ ・TVの見過ぎ
スマホから流れるブルーライトや光によって,メラトニンの分泌が低下することが報告されています。
寝つきが悪い場合や,眠れないときはスマホが原因かもしれません。なかなかスマホを手放せないですが,寝る直前までのスマホ操作は避けましょう。
まとめ
睡眠と肥満,健康は非常に密接な関係があります。睡眠が低下すると,運動の効果や肥満,病気へと繋がる原因にもなるため,注意が必要です。
この機会に,是非見直してみてください。
【睡眠と筋トレ】運動効果を出すための快眠グッズ3選|2020年
睡眠には脳を休めたり,体を休めたりといった回復機能が備わっています。ですが,日本人は不眠国と呼ばれるほど,しっかりと眠れている人は少ないんです。最近では,スマホで眠りを観察できるグッズも販売されており,簡単に知ることができるため,眠れているか知りたい人はオススメです。
本日はここまでにします。







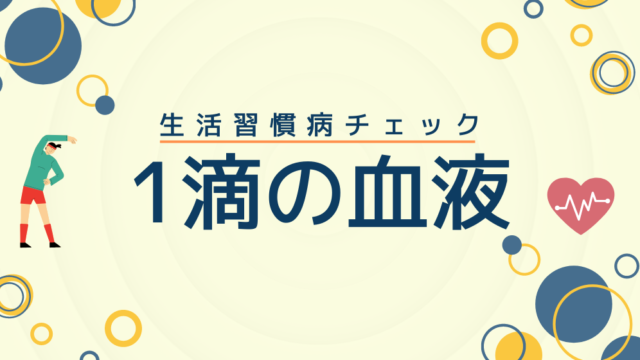







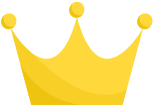 エックスサーバー
エックスサーバー 
 お名前.com
お名前.com 
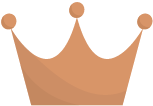 エックスサーバー
エックスサーバー 